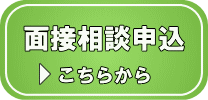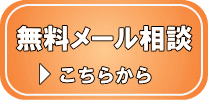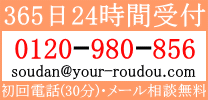| 残業代請求に関する用語 - 裁量労働制 |
| 残業関連用語集 - さ行 | |||
|
裁量労働制とは、一定の職種について、仕事の進め方や労働時間の配分を従業員にゆだね、実際の労働時間にかかわらず、定められた時間労働したとみなすことができる制度です。労働の量ではなく、労働の質や成果に応じて報酬を支払うものと言えます。裁量労働制には、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制とがあり、それぞれ導入するための手続き・要件が異なります。導入の要件を欠いたり、必要な手続きが取られていない裁量労働制は無効です。 専門業務型裁量労働制の対象となる業務は次のものに限定されています。制度の導入には労使協定を締結し、これを労働基準監督署に届け出ることが必要です。 ①新商品・新技術の研究開発、人文科学・自然科学の研究の業務 ②情報処理システムの分析・設計の業務 ③新聞・出版の記事の取材・編集の業務、放送番組制作のための取材・編集の業務 ④衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務 ⑤放送番組、映画等の制作のプロデューサー又はディレクターの業務 ⑥その他厚生労働大臣の指定する業務(コピーライター、システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、ゲーム用ソフトウェア開発、証券アナリスト、金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発、大学における教授研究、公認会計士、弁護士、建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士の各業務) 企画業務型裁量労働制は、事業運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務が対象となります。そのためどの事業場でも導入できるものではなく、本社・本店のほかは、会社の事業運営に大きな影響を及ぼす決定が行われる事業場か、本社・本店の具体的な指示を受けることなく、独自にその事業場の事業に運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画等の決定を行っている支社・支店等の事業場でなければなりません。また、企画業務型裁量労働制の導入に当たっては、労使委員会の設置、労使委員会の決議と労働金監督署への届出、対象となる従業員の個別同意の取得などの手続きが必要となります。
|