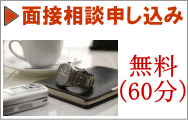|
証人の証拠調べにおいて、証人尋問を請求した当事者が最初に証人にした主尋問につづいて相手方当事者が行う尋問のことを反対尋問といいます。反対尋問は、主尋問においてされた証人の供述(証言)の証明力を弱めるために行われます。裁判所の面前での反対尋問を経ない供述証拠を伝聞証拠といい(伝聞証拠の定義には争いがあります)、原則として証拠能力が認められません。なぜなら、伝え聞いた証拠では、真実かどうかを点検することができないからです。つまり、供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の過程を経て公判廷にあらわれますが、この各過程に誤りが生じる可能性があります(記憶違いなど)。この誤りの可能性は、反対尋問によって正されるのですが、供述が伝聞証拠という形で公判廷に提示されるとすると、原供述者の誤りについて反対尋問をすることができません。そこで、伝聞証拠については、原則として証拠能力が認められないこととされているのです。例えば、証人Aが法廷で「Bが『Cの犯行を見た』と言っていました」と証言した場合、犯行目撃事実についてBを反対尋問することができませんから、Aの供述は伝聞証拠となります。
家族が逮捕されたら[HOME]
|